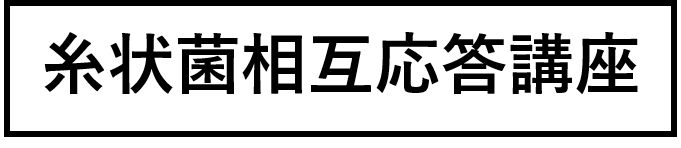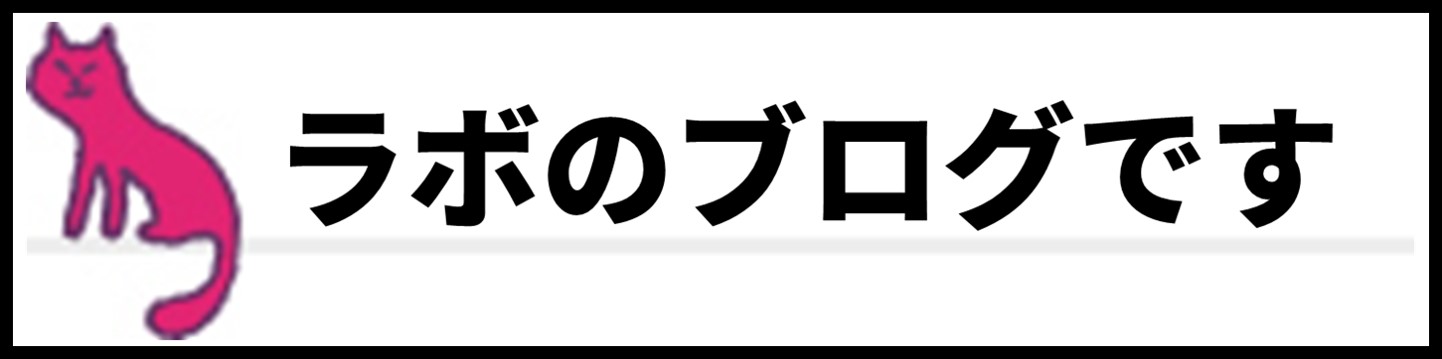University of Tsukuba, Laboratory of Biology for Extreme Molecule
研究内容RESEARCH
- RNAウイルス(≒直鎖RNA)の生態
自身の卒研テーマとして、農工大でイネの”エンドルナウイルス”に出会い、2つの疑問を持ちました。
「なぜ強いセレクションを受けているイネでウイルスが残っているのか?」
インフルエンザやコロナのように強い感染拡大力を持っているわけでもなく、宿主であるイネにちょっとでも悪影響が出れば育種の過程で排除されてしまうのに、なぜ?
「健全に見える生物にも、RNAウイルスがいっぱい潜んでいるのでは?」
ウイルスは感染症の原因として発見され、その文脈で研究が展開されてきたので、見過ごされているのではないか?RNAシーケンシング技術の発展により、実際にかなりの頻度で生物にはRNAウイルスが潜んでいることがその後明らかになり、次の疑問、「本当に全部のRNAウイルスを捉えられているの?」という話につながっています。
上記の背景のもとで、『どんなRNAウイルスが、何処で、何をしているのか』という点を明らかにする、RNAウイルスの生態学的研究を進めています。 - RNAプラスミド(≒環状RNA)の生態
RNAウイルス研究を始めると、ウイロイドという世界最小の感染性RNAのことが気になってきます。ウイルスよりも小さいのに、どうやって生きてるの!?となりますよね。しかし、ウイロイドはトップスターなので、そう容易に手を出せる相手ではありません。ごく一部の植物でしか報告されておらず、研究に必要なテクニックも特殊。しかも、植物の病原体としてはもうある程度研究が進んでいる。ということで、学生時代にはいろいろ調べましたが、結局高嶺の花には手を出せずじまいでした。
今はこのような因子が植物に限らず普遍的に存在していそうで、RNAウイルス探索用に開発した手法がウイロイドやその関連因子(RNAプラスミドと呼びます)の研究にもとても有用であることがわかり、『どんなRNAプラスミドが、何処で、何をしているのか』という、RNAプラスミドの生態学的研究を進めています。
こちらのテーマは、始めて日も浅く、どんなものが自然界に居るのかもよくわかっていないので、RNAウイルス研究と比べるとより基礎的な研究をすすめている段階です。 - 細胞外膜小胞(EV)の研究
「糸状菌相互応答講座」発足時に始めたテーマで、糸状菌が産生する細胞外膜小胞についてその産生機構の解明を目指しています。周囲の研究者のみなさんから多くのサポートを頂きつつ、ウイルス研究で培った微粒子を扱う技術を使って研究を進めています。発酵食品の中には、糸状菌が発酵の重要な部分を担っているものがいくつかあるので、そこに糸状菌由来のEVが含まれていて、それを食べた人に・・・という妄想を膨らませています。
実は裏テーマがあって、RNAウイルス&プラスミドの隠れた伝播機構となっているのではないかと考えています。
- (そしてRNAワールドと細胞誕生の接続へ?)
いつかまた。
バナースペース
筑波大学 極限分子生物学講座
〒305-8577
茨城県つくば市天王台1-1-1
生物農林学系棟
B211, B212, B112, F209, F313
TEL:029-853-6636